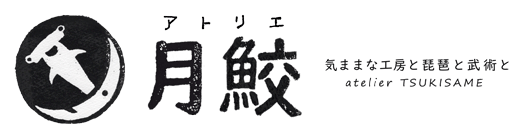津田恵月が平家琵琶(平曲)を弾き語ります。
緑に囲まれた東京・国立のアトリエ terra さんの空間で、気楽にのんびり、平家物語の世界に触れてみませんか。
今回3回目は、源平の合戦の中盤の見どころ、木曽義仲にまつわるお話を語ります。
■日時:2025年12月06日(土)16:30開場・17:00開演 (20:30閉場) 演目は以下のとおりです

<17:00~はじまりの2曲>
●『祇園精舎』(1巻1) ~約5分
はじまりに祇園精舎の冒頭を演奏します。
有名な「祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり~~」の一節が、実際にどのように語られるのかを聴いていただけます。
●『平家連署願書(へいけれんじょ がんじょ)』(7巻11) ~約20分(切り抜きバージョン)
上洛を目論む木曽義仲が、先んじて比叡山を味方につけたことを知らずに、平家一門は名を連ねて比叡山に味方になっていただくよう願い出たのがこの書状です。
すでに木曽に味方すると決めていた比叡山は、このたびは平家を見限ることになります・・・。
<休憩> 20分ほど・・・
<メイン>
●『木曽最期(きそのさいご)』(9巻5) ~約60分ほど(フルバージョンです)
 京都に入った木曽義仲ですが、所謂「官の道」を知らぬせいか天皇や官僚と軋轢を生み政治的にはうまくいきませんでした。
京都に入った木曽義仲ですが、所謂「官の道」を知らぬせいか天皇や官僚と軋轢を生み政治的にはうまくいきませんでした。
また義仲の軍が京都で乱暴狼藉をしたことなどもあり、民からも不評を買います。
この義仲の横暴を鎮めるため、鎌倉の頼朝は源義経、源範頼の追討軍を京都に差し向け、義仲軍と交戦します。
そして結局義仲は破れ果てることになりますが、妻の巴、親友であり側近でもあった今井兼平ともども、彼らの散るさまをじっくりお聴きください。
※メインの曲は長~いので、演奏中の入退場、お手洗いは自由です。
※飲み物持ち込み自由、演奏中の飲食も自由です。
※当日はterraさんでソフトドリンク、アルコールのご注文もできます。メニューは@rental_atelier_terra を参照ください。
(演奏中は周囲にご配慮願います)
※演奏後は閉場20:30まで、ご歓談などお楽しみくださいませ。
■場所:terra atelier Kunitachi Tokyo
東京はJR中央線・国立駅の近くです。
※詳細はこちらから。
■料金
ただ平家琵琶を知ってもらいたい、聴いてみていただきたい、という動機の大道芸人のような気持ちでやっておりますので、原則無料です。
平安時代の琵琶法師には、神社、仏閣をねぐらにして、寺や道端で藁筵を敷き、ヒビの入った茶碗の投げ入れ銭のチャリンという音を気にしながら、その日暮らしのびわひきの乞食(こつじき)同然の大道芸人と、一方、清潔な墨衣をまとって、貴紳宅に出入りを許され、お座敷で芸を披露し、纏まったご祝儀をいただく琵琶法師がいました。(琵琶月心会 古澤月心師匠のサイトより)
現代の琵琶法師ではありませんが、聴いてみて良かったな~と思っていただけましたら、”茶碗の投げ入れ銭”でも、お気持ちをいただければ幸いでございます・・・。

■お願い
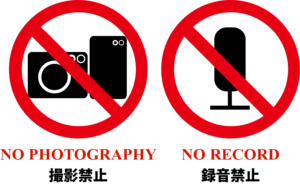
演奏や作品等の録音・録画・写真撮影はしないでください。
■津田恵月と平家琵琶(平曲)について
2014年から古澤月心氏に師事し、平家琵琶を学んでいます。
平家を知ってもらいたいという想いで演奏します。
近年は、琵琶樂人倶楽部の「平家物語を知ろう」のシリーズで演奏しています。
平家琵琶(平曲)とは──琵琶の伴奏で平家物語を語る”声楽曲”です。
略して「平家」あるいは「平曲」、以前は「平語」とも言われていました。
声楽ですので、楽器演奏そのものより「声」が中心で、しかも語り物なので「うたう」とは言わず、「語る」といいます。
室町時代(南北朝時代)に明石覚一検校が出て、曲節を定め、現行のようなものになりました。
平曲は、約200曲に分かれ、一曲ずつ作曲されています。
現代琵琶奏者が使用する譜面は、江戸中期の荻野検校が編集・集大成したものがベースになっています。
■おまけ■ 作品販売いたします(すみませんが現金決済のみとなります)
アトリエ月鮫で制作の手刺繍ブローチを、演奏の合間に会場で販売いたします。
よろしければ見ていってください。
Instagram: @atelier_tsukisame